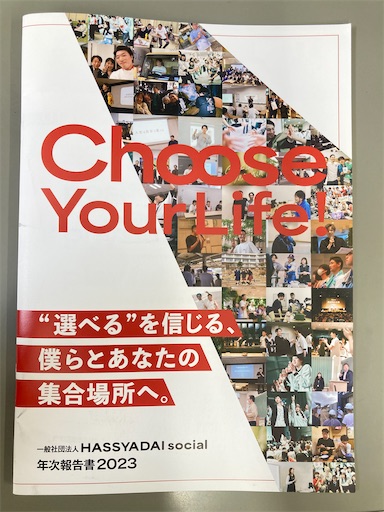
拝読させていただきました。
高校生の頃を思い返すと、選択肢は大きく分けて、指定校推薦での大学進学か、学校指定求人票での就職の二択だった。
上記二択以外は自分で考える必要があったし、教えてくれる人ももちろんいない。
いない方が普通なのか否か。
普通としないための、HASSYADAI socialさんの取り組みなのだろう。
当時の自分の人生について考える時間の圧倒的や少なさは、教員である現在も変わらない。
生徒さんたちには事あることに考えてもらう時間をとっている。しかし、いわゆるの進路希望調査になってしまう側面もある。
この活動報告を読んで、HASSYADAI socialさんは、
・選ぶ前の選択肢の材料に
・気づいた時に選択肢が狭まっていても、他の選択肢が見出せるように
・若くして働いてうまく行かなくても再起できるように
活動をされていると感じた。
若くして、就職せざる得なかった人・考える時間がなく気づいたら働いてる人たちの味方だ。
プレスリリース:トヨタ自動車×ハッシャダイソーシャル共同企画「project:ZENKAI」のプログラム第5期開催決定(PR TIMES)
↑URLのような事業を在校生や卒業生に紹介してきました。
しかし、なかなか一歩を踏み出す子は少なかった。
個人的に講演を学年に向けてやってほしいなあと画策中。さあ、私のプレゼンは学年団に届くだろうか。
私自身、子ども・パートナーとの生活で、仕事との向き合い方を、今一度考えています。
現職は約10年。採用されて2,3年は自分のやりたい仕事は、他にあるのではと常に考えていました。職場で自分のやりたいことが形にできず、力不足なのか環境が合っていないのかも判断できずにいたからです。
今となっては自分の努力と生徒とのマッチング次第で、色々な活動ができる楽しみがあります。(諦めたこともたくさんあります。)
職場で出来ないなら自分で募ってやってみたのも良かったです。↓
https://www.facebook.com/kyoshizyuku
現職には”いい意味”でこだわりはなく、2,3年目とは違う感覚で、別の仕事をしてみてもいいなぁと思っています。
2,3年目の"選ぶ”は"決断”に近かった。
奨学金はどっさりでしたし、考えるための順序・手法も、共に考える仲間も師もいませんでした。
今は多くの方々のおかげで、自分次第で生き方が決められるのだと思えます。パートナーからも、昨年の育児休業ワンオペの経験から専業主夫の適性を指摘され、退職を勧められいます。笑
そう考えると、選ぶには多様な立場の人との関わりや支えが必要です。
今の仕事を辞めても、次の仕事が大外れでも、大失敗しても生きていけそうな安心感が、私にとっては大切なのだと思う。
そして、その”選ぶ”に至る環境や条件は人それぞれ違うのかもしれません。
(上記サイトより)
「それでもなお、」
というところが、惹かれますし、気になります。共に仕事ができるように動いてみます。