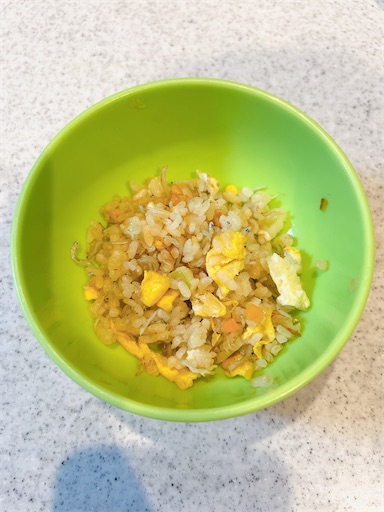- ・ブログ概要
ブログ管理者プロフィールはこちらです。↓
https://www.facebook.com/ryo.nishio.90
教員をしながら、「教師塾」という学習・交流団体を主宰・運営しています。
https://www.facebook.com/kyoshizyuku
職場や教師塾での活動記録や、日々感じること、生徒へのメッセージなどを書き残しています。
ブクログで読書記録しています。
共通の本を読んでいたり、共通の積読がありましたら読書会をしましょう!
・カテゴリー説明
ブログトップページから、カテゴリー別に記事が見られます。
1. 教師塾
2016年に活動を始めました。こちらが活動理念です。
教員として学校中で生活し、一般社会との感覚の差が開く危機感がありました。
教員こそ外へ出て社会(教員以外の人)との関わりを持ち、学校内だけ出なく普遍的に学ぶ必要のあることを模索し、学びの場を開く重要性を感じてます。学習・交流会は20回を数えました。
これまでのように楽しみながら、明日の生活が少しでも変化がある場にしていきます。
2. 寺子屋塾 中村教室
学びのメインツールの一つである「らくだメソッド」を毎日取り組んで(取り組もうとして)います。通塾は原則週に一度で、教材を持ち帰って自宅で学習します。
この塾は、何をどう学んでいくかは塾生によって様々です。寺子屋塾が用意する学びのツールから得られる学びや、自覚する課題は人それぞれ違うからです。
私は、「自ら学ぶ。」とは一体どういうことかを一から体験しているところです。
また、寺子屋塾では「日常が本番」といわれており、
職場では人(生徒)が、「自ら学ぶ。」に向かうには私はどう関わればいいのかを試行錯誤している日々です。
寺子屋塾の学びのツールの一つである、「未来デザイン考程」という思考フレームを身につけるワークショップの振り返りもこのカテゴリに含まれています。
3. らくだメソッド振り返り
寺子屋塾中村教室のメイン教材であるらくだメソッドについて
ホームページにも書いてありますが、学習者が教材を決め、学習するペースを自分で決めます。
通塾した際に、一週間の学習通して感じたことなどを書き残しているのがこのカテゴリです。
自分が進んで学習できるようになってくる経過を私なりの言葉で表現しています。
4. 学校
現在の勤務校での出来事からしか私は言えることがありません。
学校全体や教育全体に対しての物言いになっている記事は、勤務校を想像して書いているんだと思って頂けると幸いです。
5. 各種通信
クラスや、部活動生徒に向けて通信を書いています。ミーティングで伝えきれなかったことや、考えの前提などを書いて発信しています。
6. 哲学対話
哲学対話は、教師塾で行うワークショップの一つで、教師塾でも、学校でも行っているものです。